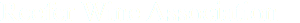第六回
グラスワインの功罪
なかなか先に進めず申し訳ありません。前回、会員用の連載にグラスワインのことを書きましたので、ここで触れておきたいと思います。筆者が危惧しているのは、昨今、グランメゾンを中心にワインペアリングが流行っていることです。これは、供されるそれぞれの料理に合うグラスワインをセットにして提供するというものです。しかし、これはグランメゾンがアラカルト中心から、いわゆる「お任せ」メニュ一主義に転換したことと関係があります。そこで、料理の「お任せ」主義批判の際にワインペアリングについてはその問題点を論じたいと思います。その前提として、グラスワインそのものが極力避けるべきものであるということを示したいと思います。
まず、グラスワインを飲んでその銘柄の資質を推量できるのは相当ワインを飲み慣れている者でなければ無理ということ。つまり、初心者ほどボトルでワインを頼む必要があるということです。その理由は簡単です。グラスで出されたワインがいつ抜栓され、どのような状態で保存されていたかをソムリエに確認する勇気が皆さんにあるか、ということです。つまり、誰にも聞かず、自分の五感だけで、このグラスワインがどのくらい前に抜栓され、どのような状態で(例えば、ヴァキュヴァンなどで空気を抜かれて)保存されていたのかを言い当てることができるとしたら、それは相当なテイスティング能力の持ち主としかいいようがありません。
グラスで供する限り、時間差が生じます。従って、デリケートなオールドヴィンテージなどをグラスワインで供するのは、人数の決まったワイン会などでない限り、無理と言えます。そこで、どうしても若いワインを用いるしかありません。そうなると今度は、目の前でボトルを開けてそれが自分にグラスワインとして供された場合、素直に喜んでいられないことになります。何故なら、何時間後かに供されても問題ないワインです。開けたてはかえって硬くて美味しくない可能性大です。つまり、目の前のグラスワインがその銘柄の美味しい状態=本来あるべき味であることの方が稀と言えるのではないでしょうか。そして、そうした状況下でそのワインのあるべき姿を推測できるのは、相当ワインを飲み慣れた者でない限り無理なのは、容易に想像できるかと思います。
さらにグラスワインで供されるのは、若いだけでなく、その店でも比較的リーズナブルなワインであることは必然です。何故なら、高級ホテルでもない限り、割高なグラスで一杯2000円、3000円といったグラスワインが飛ぶように捌けていくことなどあり得ないからです。昨今、料理とワインのマリアージュなどと声高に叫ばれていますが、グランメゾンで供される一流の料理にグラスワイン程度のワインを合わせて、ベストマリアージュなどと言うのはお門違いも甚だしい。これこそ、ワインペアリングが胡散臭い理由です。本当にその一流店の料理にふさわしいグラスワインをマリアージュしていたら、ワイン代だけで一人数万円になってしまうのではないでしょうか?しかも、デリケートなヴィンテージものを合わせることが出来ないとしたら。つまり、ワインペアリングという発想そのものが、生産者を招いての人数限定の特別な催しでもない限り、無理なのです。
こうしてたどり着く結論は、初心者ほどボトルでワインを頼むべしということです。グランメゾンなら、それ相応に良いワインを選ぶこと。その助けにソムリエがいるのですから。目の前で抜栓され、注がれてすぐのテイスティングの状態から、ワインがどのように変化し、美味しさがどこで頂点に達するか、食事を通して確認すること。この体験の繰り返しなくして、ワインを知ることは出来ません。
こうした意味でも、レストランがドゥミ・ブテイユ(ハーフボトル)をリストに揃えることを推奨します。グラスを頼む客で、あまり飲めないからという方もいらっしゃるからです。
グランメゾンに行ったら、ハーフであれ、ボトルでワインを頼むのが客としてのマナーではないでしょうか。筆者の唱える「レストランの正三角形」は提供する側だけではなく、まさに、一流の料理に、一流のワイン、それを一流のサーヴィスで提供してもらうよう、つまり正三角形を描くよう、客自らが配慮する必要があるのです。
ドゥミはドゥミで普通のブテイユ(ボトル)より早く熟成するので、それなりの楽しみ方があります。ちなみに、(瓶)熟成に一番適しているのは、マグナム(1500ml)と言われています。昨今のレストランがドゥミを置かないのは残念です。相手が飲まない人とのデジュネで、ホテルならと思い、帝国ホテルのラ・ブラッスリーでグランドリストを見ましたが、ドゥミがまったく置いていなくてガッカリしました。結局、ボトルで頼んで半分持って帰ることに。置いてこようかと思ったのですが、エチケットが欲しかったので(笑)。
最後に、グラスで推奨できるのは意外にもシャンパーニュでしょうか。炭酸が抜けていればクレームすればよい訳です。また、グラスで出るのはヴィンテージものではないでしょうから、いわゆるノンヴィン、どのメゾンも自身の味を一定に保つことを第一に調整していますので、スティルワインのような味の違いが生じることは少ないと思われるからです。
第七回
テイスティングに関する一考察
先日、ある会合の後ワインを飲むことになり、折角なので飲み比べましょうとホストから興味深いプレゼンテーションがなされました。それは、ブルゴーニュの有名なネゴシアン、フェヴレ(Faiveley)社の一番ポピュラーなブルゴーニュ2014年とアロース・コルトン村(正確にはラドワ・セリニー村のル・ロニェ・エ・コルトンの一角)に単独で有している(モノポール)、グランクリュのコルトン(クロ・デ・コルトン・フェヴレ)2012年だったのです。値段的にも10倍ほど違う二本でしたし、もちろん、専門家もいらしたので、どちらがコルトンかというような比較ではありません。それは筆者でも色と香りを嗅いだだけでわかります。ホストの問いは「共通する点があるのでしょうか」というものでした。いわば「フェヴレ味」とでもいうものがあるのか、と。酵母は一緒だろうから、ある程度はあるのではないか、など興味深い見解が寄せられました。
目の前にワインが出されてのテイスティングに関しては、ぜひ、当協会のコンディション判定講習会や今後認定を行なう予定の資格の認定講習会などに参加され、基礎から本格的なものまで、ご自身のレヴェルに応じて、専門家に指導していただくことをお薦めします。今日は実際にテイスティングした後、飲みっ放しにするのではなく、それを整理し、蓄積して行くことによって、感能的だけではなく、理性的にもテイスティング能力を伸ばして行く方法を、心理学を援用して、提示してみたいと思います。
筆者はワインを飲んだ次の日、剥がしたエチケットを再び出して、並べます。そして、それぞれのワインの色、香り、味わいをもう一度思い出してみるのです。これは、夢の解釈する際に用いる方法です。朝、昨晩の夢を思い出そうと努力すると思い出せるようになるのです。人間の脳には生まれてから死ぬまですべての記憶が残されているからです。そして、さらに過去に飲んだワインから比較できるようなものがなかったか、探してみるのです。筆者の場合、偶然にもその数日前、同じフェヴレ社の造るニュイ=サン=ジョルジュ、プルミエクリュ、オ=シェニョ2007年を飲んでいたのです。そして、それをも加味して、比較してみる。すると、ブルゴーニュはコルトンよりニュイ=サン=ジョルジュの方に近い味がしたと思われたのです。
さて、問いは「フェヴレ味」があるか否かでした。確かにACブルゴーニュは大手ネゴシアンから家族経営のドメーヌまで星の数ほどあると言っても過言ではありません。しかも、手作り感満載のドメーヌ物が個性的なのはもとより、ドルーアン、ブシャールと言った何処でも見かける大手メーカーのものでも確かにそれぞれ味が違う。では、やはり「フェヴレ」共通の味はあるのでしょうか。
この際、筆者は「類推」を用います。つまり、ブルゴーニュではなく他のワインで考えてみるのです。例えば、ブルゴーニュときたら、ボルドーが思い浮かびます。そして、こう置き換えてみるのです。「ムートン・カデを飲んで、シャトー・ムートン=ロットシルトがわかると言えるだろうか」、と。ボルドー好きであれば、これは乱暴な物言いだと思うでしょう。確かにムートン・カデもACボルドーで同じバロン・フィリップ・ド・ロットシルト社が造っているのですが、シャトー・ムートンの畑の葡萄から作っているとは思えません。他の畑の葡萄を買っているのか、ワインそのものを買っているのかわかりませんがいずれにせよブレンド物であることに変わりはないと思われます。フェヴレも同じで、いくらブルゴーニュの大手ネゴシアンとはいえ、自社所有の畑の葡萄からACブルゴーニュを作っているとは思われません。とすれば、同じフェヴレでもコルトンとACブルゴーニュではほぼ共通点はないと結論付けてよいのではないでしょうか。もちろん、ドルーアンのACブルゴーニュとは違うでしょう。それは、ACブルゴーニュという平行関係の中でのブランドごとの味の違いに他なりません。
もちろん、小さなドメーヌで同じ畑で作られたワインが、例えばフィクサンとACブルゴーニュで売られた場合、それらに類似性があり、そのドメーヌの味があると言うことは出来るでしょう。しかし、大手ネゴシアンの場合は、ACブルゴーニュと自社畑から作られるワインは別物と考えるのが妥当だと思われます。
テイスティングはその場で精確に判定することがもちろん大事です。しかし、後でもう一度記憶と情報を加味して考察し直すことで、その能力はより精度を増すと考えられるのです。
第八回
『ゴー=ミヨ 東京・北陸』刊行に寄せて ①
あの『ゴー=ミヨ』が日本に進出し、東京・北陸版が出たことを皆さんはご存知でしょうか。思えば、『ミシュラン2008』の東京版が出るというので連日マスコミが大騒ぎだったのから十年が経とうとしています。その折、筆者もまた、『日刊ゲンダイ』紙が「ランチで使えるミシュラン」という連載をすることになり、縁あって記事を書くことになりました。和食もと言われましたが、専門外ということでフレンチを中心に西洋料理だけ(コンラッドのヌーヴェル・シノワーズ「チャイナ・ブルー」には参りました)にしていただきました。さらに、責任を持とうと署名記事にしてもらったのです。それでも星付きの店を十店は訪れたと思います。というのも、ミシュラン東京版は当初、星付きの店だけ150店が掲載されたからです。
『ゴー=ミヨ』はミシュランに対抗すべく、1972年、アンリ・ゴー(1929~2000)とクリスチャン・ミヨ(1928~)によって刊行されました。二人はすでに1962年からジュリアード出版のパリガイドブックを担当し、1968年には新たにパリ近郊までも含んでの「新しいガイド」を出版し、満を持してフランス版を刊行したのです。ミシュランの「星(アステリスク)」に対して、ゴーミヨは「トック(コック帽)」で最高五トックとし、さらに画期的だったのは二十点満点で点数をつけたのです。ミシュランの保守主義に対し、ゴー=ミヨはヌーヴェルキュイジーヌを奨励しました。筆者も二十年ほど前、海外研究でパリを訪問していた時期、ミシュランとゴー=ミヨ両方を参考に店を選んだものです。ミシュランでは一つ星でもゴー=ミヨでは二つ星級の評価をされている店は大抵訪れました。例えば、九区にあったコンティチニ兄弟の「ターブル・ダンヴェール」など。あまりの料理の奇抜さにちょっとついていけない感じでしたが(笑)。
そんな『ゴー=ミヨ』が日本にも進出したのですが、どうもそれほど話題になっていないように思われるのです。料理記事を書いているライターの友人に聞いても知りませんでした。どうも、様々なトラブルがあったようなのですが業界人でもない限り、大事なのはあくまで中身です。そこで、比較すべきはまず、もちろん『ミシュラン 東京』でしょう。さらに、両ガイドとも、パリ版を出していますので、首都のレストラン評価として比較の参考になるかと思います。
そこで、まず気になるのは、『ゴー=ミヨ』におけるトックと点数の関係、さらには、トックが五段階評価である限り、ミシュランの三段階評価とどのように対応しているのか、ではないでしょうか。19.5点~19点が五トック、18.5点~17点が四トック、16.5点~15点が三トック、14.5点~13点が二トック、12.5点~11点が一トック、さらに10.5点~10点がトックなしですが記載されています。これは、パリ版と全く同じです。ただし、一トックはbonnes tables 、トックなしはbonnes adressesというのが原語です。トック付きはすべてtableですので、日本版の一トックが「良いレストラン」、トックなしが「美味しいレストラン」という表記とは異なっています。パリ版では、一トックが「美味しいレストラン」、トックなしは「美味しい店」くらいでしょうか。ここに、「レストラン」とは何かという筆者の常に提起している問題が見え隠れしているのが読み取れます。さらに、ゴーもミヨも20点をつけることはあり得ないと公言していましたので、19.5点が最高点になっています。ただし、2004年の『ゴー=ミヨ フランス』でサヴォア地方にあるマルク・ヴェイラの店二軒に20点満点をつけて物議を呼んだのです。ゴーはすでに他界し、ミヨも一線から退いていた状況での出来事でした。
ちなみに、東京の最高点は19点で四軒。カンテサンス、ジョエル・ロブション、神楽坂石かわ、龍吟と和洋それぞれ二店ずつです。パリ版(2016年、2017年は未刊)も最高点は19点で、ギー・サヴォワ、アルページュ、ル・サンク、ルドワイヤン、ガニェール、アストランス、プレ・キャトランの七店でした。
さて、問題はミシュランの星との対応関係です。筆者の見るところ、「東京版」に限って言えば、2.5点刻みで、17.5点までが三つ星。17点~15点までが二つ星、14.5点~12.5点までが一つ星と考えてよいかと思います。
というのも、ミシュランの三つ星は12店。ゴー=ミヨの17.5点までの店は13店だからです。かの有名な、すきやばし 次郎本店は17.5点。ただし、ミシュラン三つ星で西洋料理の店は、カンテサンスとジョエル・ロブションだけです。ゴー=ミヨになると、17.5点までに、さらにロオジェ、エスキス、レフェルヴェソンスが入り、和食が減ります
一つ星の要件ですが、12.5点なのか13点なのか迷うところです。13.5点であれば、確実に一つ星なのですが。二つ星も同じで15.5点なら確実に二つ星で、15点は意見が分かれるところか、と。12.5点までにしたのは、『ミシュラン 東京』発刊以来、現在に至るまで一つ星を守っているレザンファン・ギャテが12.5点だからです。
こうして、ミシュラン初年度は星付きの店だけだったのに対し、ゴー=ミヨはそれ以外の店にも評価を広げた点は先達に学んだといってよいでしょう。では、次回は内容について見て行くことにしましょう。
第九回
『ゴー=ミヨ 東京・北陸』刊行に寄せて ②
前回に引き続き、『ゴー=ミヨ 東京・北陸』を『ミシュラン 東京』、『ゴー=ミヨ ギッドパリ』などと比較しつつ、その特徴を検証してみたいと思います。なお、個々の店の評価はここでは検証せず、全体の構造や評価の基準などについて、特にフランス料理を中心に見て行くことにします。
まず、『ミシュラン 東京』が初年度、星付きの店だけだったのに対し、『ゴー=ミヨ』は星なしに相当する一トックやトックなしの店も掲載されています。それが可能であった理由は『ミシュラン』に比べ、ジャンルを限定したことにあるかと思われます。つまり、西洋料理は原則、フレンチとイタリアンのみ。和食は「懐石系」と「寿司」だけに限定し、蕎麦や鰻は含まれていません。つまり、コース(的に)で食べるものに限っているのです。そして、本全体の前半が西洋料理。後半は和食で、「懐石系」と「寿司」をジャンル別に分け、区ごとに掲載しています。『ミシュラン』がジャンルに関係なく、あいうえお順であるのと対照的です。従って、中華は載っていません。今後、ジャンルを増やすことになるかと思いますが、筆者はジャンルに関してはこのままでよいのではないかと考えます。『ミシュラン』のように、ラーメンや焼き鳥の店が星を取るのはいかがなものか、と。レストランである以上、料理のみならず、サーヴィス、ワイン(日本酒)なども総合的に評価すべき(レストランの正三角形)ではないでしょうか。
さて、『ゴー=ミヨ』を『ミシュラン』と比べて、気が付くのは、まず、ミシュランには掲載されていない往年の名店が数多く登場していることです。「オテル・ド・ミクニ」(17点)、田代和久シェフの「ラ・ブランシュ」(15点)、五十嵐安雄シェフの「ル・マノワール・ダスティン」(14点)など、その評価も高く、妥当と思われます。さらに、セルリアンタワー東急ホテルの「クーカーニョ」(13点)、パレスホテル東京の「クラウン」(15.5点)、東京ステーションホテルの「ブラン ルージュ」(14点)など、やはり『ミシュラン』には載っていないホテルのメインダイニングを多く見い出すことができます。ここから推察されるのは、斬新なものだけではなく伝統的なものをも尊ぶこと。さらに、ホテルのレストランに顕著なサーヴィスという点を重視していることです。これはそれぞれのレストランの評を見ても明白で、短い文章の中に、ワインについて、店構えやサーヴィスについてなど、料理の評価のみならず、レストラン全体について評価するよう配慮されています。
こうした傾向は、一見したところ、本来の『ゴー=ミヨ』の立ち位置とは逆に見えるかと思います。というのも、『ミシュラン』の伝統・権威重視に対し、『ゴー=ミヨ』は「ヌーヴェル・キュイジーヌ」を推奨すべく登場してきたのですから。しかし、『ミシュラン』の料理至上主義は現主幹、ジャン=リュック・ナレになってからと言われています。その点、『ゴー=ミヨ』はヌーヴェルを尊重しつつ、あくまで「レストラン評」という総合的判断を維持しているということでしょう。
そうした『ゴー=ミヨ』の姿勢がわかるのは、各レストランの評価の前に置かれた「各賞」の受賞です。こうしたコーナーは『ミシュラン』にはありません。今回の『ゴー=ミヨ 東京・北陸』には、「今年のシェフ賞」、「トランスミッション賞」、「イノベーション賞」、「明日のグランシェフ賞」、「期待の若手シェフ賞」が掲載されています。「今回の」と限定したのは、このコーナーは次回からどうなるかわからないからです。
実は『ゴー=ミヨ』パリ版は本全体の構成がころころ変わり、ホテル評が載ったり載らなかったり、ワインバーやパン屋(ブランジュリー)など他の形態の飲食店・食料品店が掲載されたりと毎年、蓋を開けてみないとわかりません。この冒頭のコーナーも、2015年版では「お気に入り」として、それぞれの理由を挙げて店が掲載されています。例えば、「今年のビストロ」として七区の「ガール・オ・ゴリル」、「最も景色の良い」として十六区の「ロワゾ・ブラン」、「今年の日本人」として五区の「レストラン A.T」などが挙げられています。しかも、この年は点数がなく、トックだけで評価されています。
そして、2016年版(2017年版は現時点で未刊)では再び点数が復活し、冒頭のコーナーは『ゴー=ミヨ フランス』の再録でパリに限定されているわけではなく、フランス全土での評価です。従って、例えば「今年のシェフ」はフランス北部パ・ド・カレー県、ラ・マドレーヌ・ス・モントルイユ村にある「ル・グルヌイエール」(2015年版『ミシュラン』一つ星)のアレクサンドル・ゴーティエに送られています。このように、今後『ゴー=ミヨ 東京・北陸』がどのように展開していくかはパリ版の動向と共に注視していく必要があるでしょう。
筆者としては、「明日のグランシェフ賞」と「期待の若手シェフ賞」を重視しています。どちらもこれからの活躍に期待をかけての受賞ですので、『ゴー=ミヨ』の評価の傾向が窺い知られるからです。なお、両賞の今回の受賞者については会員頁でさらに考察することにします。また、「明日のグランシェフ賞」受賞三店については、実際に食事に出かけ、筆者なりの評をブログ(「関修のトポスアクティブ」、http://ameblo.jp/ozamyu/ )に掲載する予定ですので、そちらをご参照いただければ幸いです。
第十回
ザガットから食べログへ
善良なる素人の食通(グルメ)という幻想
皆さんは『ザガット』というレストランガイドを覚えていらっしゃいますでしょうか。ミシュランが日本に上陸する前、大変重宝がられたガイド本でした。筆者の家の近くの本屋にもレジの脇に積んで置いてありました。外国の権威あるレストランガイドの日本版ということで、ミシュランの日本版が登場すると入れ替わりに、その姿を消していったのでした。
ところで、この『ザガット』、ミシュランやゴー=ミヨとは一線を画しているガイドです。それは、調査方法にあります。ミシュランやゴー=ミヨなどフランス出自のガイドは、主幹の評論家や調査員によって評価されます。それに対し、1979年、ニューヨークの弁護士ザガット夫妻が、そうした特定の専門家による権威的な評価に頼るのではなく、食を愛する一般の人々へのアンケートを統計的に処理することで評価する方法を考案。その結果をガイドブックにしたのです。あくまで利用者の立場にたっての民主主義的かつ実用的なレストランガイドというわけです。とりわけ、アメリカでは、投票に参加するのが、食に対する知識を有し、さらには民度の高さを表わすものとして、『ザガット』を持ち歩いて利用することがビジネスマンのステイタスになる程でした。
こうした『ザガット』の方法論は、SNSの普及とともに一般化していったと言えましょう。実際、その後、ザガットはレストランのみならず、ホテルはもとより、航空会社や映画などの格付けも行い、2011年にグーグルに買収されています。つまり、『ミシュラン』の日本上陸が『ザガット』との交代劇を生んだだけでなく、時代がSNSで「ザガット」に代わるサイトを運営することを可能にしたということが言えるでしょう。実際、まず、「ジバラン」という自腹覆面レストラン評価サイトが1996年から2006年まで運営され、話題になり、本も出版されています。これは、ミシュランの調査員の役回りを一般のフレンチ愛好家たちが行ない、自分たちで評価しようという試みでした。これもSNSでの反響あってこそ、書籍化されたのでした。そして、2005年にはまさに「ザガット」の日本版ともいうべき、「食べログ」が「ランキングと口コミで探せるグルメサイト」として登場するのです。
「食べログ」の影響力の大きさは周知のとおりです。5点満点の評点、ユーザーの「口コミ」が売り上げを大きく左右し、結果、やらせや風評被害による訴訟など様々なトラブルも絶えることがありません。そして、つい最近もトップレヴューアーが特定の飲食店から過剰な接待を受けていたと報道され、ワイドショーなどでも大きく取り上げられたのでした。これは、やらせ防止効果も狙って、評価の基準を「ユーザー影響度」と称する「加重平均」に置いていることと関係があります。つまり、初めて評価した人の点数はまったく採用されず、そのレヴューの数に応じて、点数への反映度が増していくというしくみなのです。従って、1000件を超すレヴューを載せていたその人物は、カリスマレヴューアーとして絶大なる影響力を持っていたのです。実際、本の出版、TVへの出演なども多々行っているようです。確かに、本業は社長か何かで「自腹」でレヴューを書かれているのでしょう。しかし、TVへの出演はグルメで有名な芸能人の推薦とか、ワイドショーのコメンテーターのタレントが一緒に食事したことがあると発言するなど、普通の「素人」であるはずがありません。また、グルメイヴェントのプロデュースまで行なうとなれば、利用者の立場というより、仕掛人、まさにいかに利益を上げるかといった店側の立場に立っているのではないでしょうか。
結局、レヴューアーそのものが権威化してしまうのです。しかも、特定の。これは、例えば、ファッションモデルが「読者モデル」化しているのと似ています。しかし、よく考えてみれば、SNSそのものがブロガーやユーチューバーなどそれを生業にしている者たちを生み出しているのです。これは、いわば「素人の顔をした商売人」ではないでしょうか。まさに、素人っぽいところがユーザーに親近感を持たせ、自分も「権威」=大衆を「操作する」側になれるのでは、という幻想を持たせるのです。
しかし、だからといって、例えば、数値化だけにしてレヴューなしにする、あるいはレヴューもユーザーのからのものを集約して再構成し、誰のものかわからないようにする、など完全な匿名化を図り、カリスマレヴューアーなど登場し得ないスタイルにしたら、誰も投稿しなくなるでしょう。フェイスブックにせよ、インスタグラムにせよ、SNSの大きな魅力は「自己顕示」なのですから。そして、「権威」に弱い。それがカリスマレヴューアーなのか、ミシュランかの違いだけであって、その心理的メカニズムは変わらないのです。
おわかりでしょう。まさに、批判精神が欠如しているからこそ、情報に踊らされてしまうのです。そして、「人任せ」の一般ユーザーは、「自己責任」という名のもとに非を背負わされてしまうことになるのです。「批評」とは、それを理解することで、一人ひとりが自ら批判精神を養い、意識して事に当たるようになることを期待して書かれるものなのです。美食の主体は他ならない、客である「我々」なのですから。
目次
著者Profile

関 修(せき おさむ)
フランス現代思想
文化論
(主にセクシュアリティ精神分析理論/ポピュラーカルチャースタディ)
現在、明治大学法学部非常勤講師。
2014年、明治大学で行われた「嵐のPVを見るだけの授業」が話題となった。
経歴
1980年:千葉県立船橋高等学校卒業
1984年:千葉大学教育学部卒業
1990年:東洋大学大学院文学研究科哲学専攻博士後期課程単位取得満期退学、東洋大学文学部非常勤講師
1992年:東洋大学文学部哲学科助手
1994年:明治大学法学部非常勤講師 、他に、岩手大学、専修大学、日本工業大学などで非常勤講師を務める
著書
『挑発するセクシュアリティ』(編著、新泉社)
『知った気でいるあなたのためのセクシュアリティ入門』(編著、夏目書房)
『美男論序説』(夏目書房)
『隣の嵐くん~カリスマなき時代の偶像』(サイゾー)
『「嵐」的、あまりに「嵐」的な』(サイゾー)
翻訳[編集]
G・オッカンガム『ホモセクシュアルな欲望』(学陽書房,1993年)
R・サミュエルズ『哲学による精神分析入門』(夏目書房,2005年)
M・フェルステル『欲望の思考』(富士書店,2009年)
関修公式WEBSITEへ ▶︎